
いざ相続することになったものの、
また、
被相続人の遺言によって、
さらに、
相続したら、
そこで、
相続でありがちな疑問と、

遺産はどのように分割すればよいか?
被相続人の財産について、
遺産分割です。
相続人が全員参加して行い、
相続人全員の同意が必要ですが、
また、
相続人全員の合意があれば、
法定相続分に関わらず、
分割の実行は、
まず相続人の協議によってなされ、
家庭裁判所では、
まず、
調停が行われ、
遺産分割審判が行われます。
分割手法としては、
(1)現物分割
(相続財産をそのままの形で相続人に分配する)
(2)換価分割
(不動産の全部又は一部を売却し、その代金を相続分に応じて分配する)
(3)代償分割
(
(4)共有
(不動産の全部又は一部を相続人全員の共有とする)
があります。
相続すると不利益になる場合は?
相続の対象となる財産には、
不動産や預貯金等の積極財産(
借入金などの消極財産(
そこで、
相続が開始したときに、
相続の効果を受け入れるかどうか
相続の承認、放棄です。
承認には、
単純承認と限定承認があり、
限定承認とは、
相続財産の範囲内で債務を支払い、
債務が膨大だが積極財産も多く、
自己に相続があったことを
知った時から3カ月以内に
被相続人の住
申述することになります。
ただ、
相続人が複数いる場合は、
全員の合意が必要です(
相続の効果を受け入れないならば、
知った時から3カ月以内に
被相続人の住
申述して相続放棄をすることができます。
これにより、
代襲相続もできなくなります。
相続放棄は、
他に相続人がいても一人でできます。
遺言書は本人でなく代筆でも可能?
被相続人が、
生前に、
被相続人が自分で作成する自筆証書遺言について、
従前は、
今般の相続法改正により、
相続財産の目録については、
他人が代筆したり、
方式が緩和されました。
これにより、
高齢者でも自筆証書遺言を作成しやすくなり、
遺言の利用促進に資することとなります。
また、
新たに、自筆証書遺言を公的機関(法務局)
これにより、
遺言書の紛失、改ざんのおそれがなくなり、
また、
遺言により、取り分が少ない場合は?
遺言は、遺言者の意思を尊重するものです。
しかし、
その内容によっては、
相続人のなかには、
生活に困窮するこ
不都合が生じます。
このような不都合を緩和し、
調整するのが遺留分制度で、
遺留分とは、
相続人に最低限保障される取り分ということになりま
遺留分の割合は、
直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
相続人である場合は相続財産の3分の1で、
(
各相続人の遺留分割合は、
そのうちの法定相続分割合となります。
ところで、
遺言ないし生前贈与により遺留分の侵害があった場合、
侵害された相続人が、
遺留分相当分が遺留分権利
当然に物権状態(共有)が生ずるとされました。
2019年の相続法改正により、
遺留分権利者に遺留分侵
そして、
金銭請求を受けた受贈者ないし受遺者は、
期限を許与してもらうこと
2019年の相続法改正も踏まえ、
※本記事の記載内容は、2020年2月現在の法令・
引用
メルマガ
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0629
FAX番号 052-331-0317
酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資
【100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方
不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる
【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。


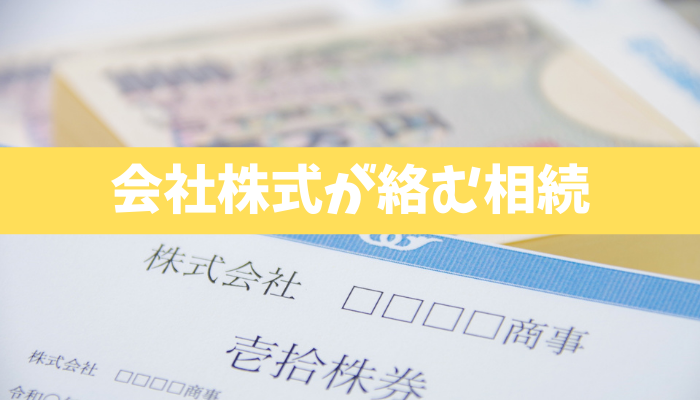
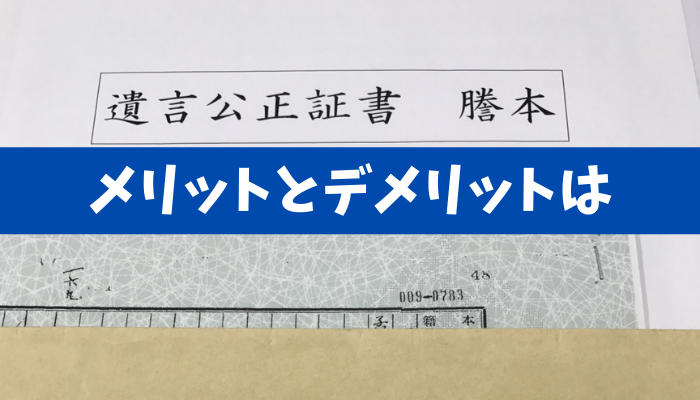
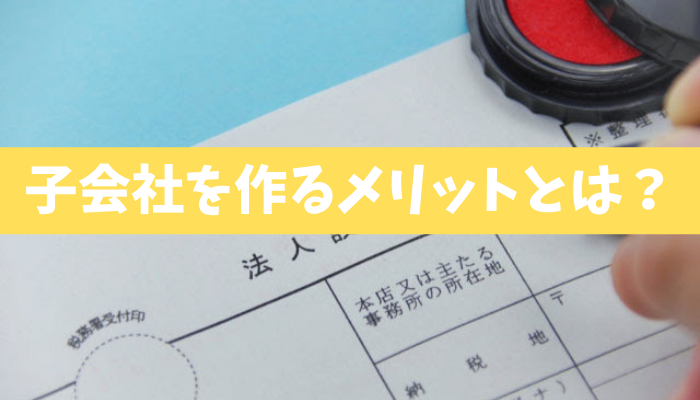


コメントを投稿するにはログインしてください。