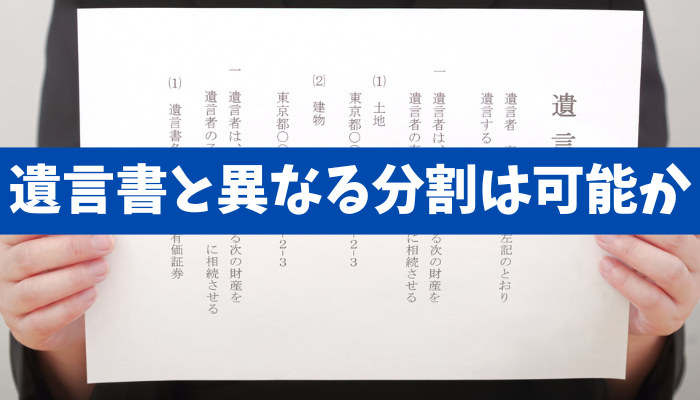胎児が相続人になる場合の相続税の計算について、
解説します!
相続の対象となるご家族の中に胎児がいるとき、
法律上は「すでに生まれたもの」として相続権を有します。
しかし、
相続税の計算では少し取り扱いが異なります。
胎児が相続人となる法的な考え方
・民法では、胎児は「相続開始のときに生まれていたもの」として扱われます。
そのため、法律上は相続権を持っています。
・しかし、「相続税」の世界では、実際に出生していなければ、
申告期限の時点では相続人の数に含めずに計算します。
相続税計算の具体的な流れ
. 1、申告期限までに胎児が生まれなかった場合
・申告書の提出時点でまだ生まれていない胎児は、
相続人の数に含めません。
よって、遺産に係る基礎控除額や相続税の総額なども、
「その胎児がいないもの」として計算します。
2、その後胎児が無事に出生した場合
出生すると、結果的に「相続人が増えた」ことになります。
その結果、基礎控除が増えたり、
相続税の総額が変わったりする場合があります。
・もし、出生によって相続税が減る場合は、
一定の期間内(原則5年以内)に「更正の請求」をすることで、
多く納めすぎた税金を返してもらえます。
大切なポイント
・胎児が申告書提出日までに生まれていない→
相続人にカウントしない
・出生したら→
更正の請求で精算可能
法律と税法で取り扱いが違っている、
という点が今回のキモなんです。
相続人の確認は、
単に家族構成を見るだけでなく、
「お腹の中に赤ちゃんがいるかどうか」
も大切なチェック項目になります。
胎児の場合は民法と相続税法で扱い方が違うので、
そこを正しく理解しつつ、
いざというときに、
更正の請求などの手続きをスムーズに進められるよう準備しておきましょう。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。
失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!
【失敗しない不動産投資の事業計画書】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方